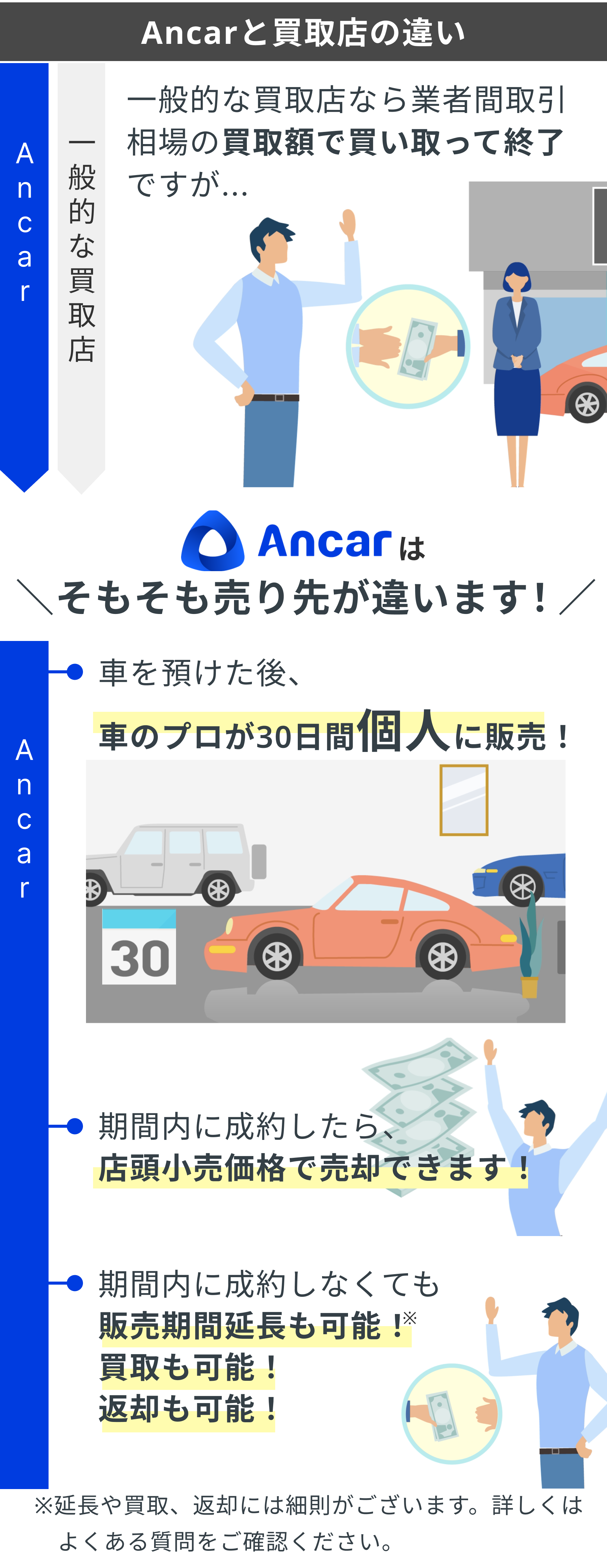信号で「赤・青・黄」が使われている理由を知っていますか?
今までに1度は信号の色について疑問に思ったことはあるはずです。
- 「信号の色って意味あるのかな?」
- 「そもそも、なんで緑を青って呼ぶの?」
- 「信号ってなんで赤・青・黄なんだろう?」
こんな疑問に答えるために、信号にまつわる豆知識をまとめてみました。
信号の歴史

まずは信号の歴史について見ていきましょう。
世界初の信号機
1868年、世界初の信号機は、イギリスのロンドンで誕生しました。
その世界初の信号は、馬車の交通整備するために使われました。しかし、これは現在のような信号機ではなく、光源にガスを使った手動式でした。そして、3週間後、ガス漏れが原因で爆発事故が発生。ただちに撤去されることに。世界初の信号はなんとも悲しい結果に終わってしまったんですね。
電気式信号の歴史
世界初の信号は悲しい事故を起こしてしまったものの、交通整理のための手段として普及していきました。
1900年代に入り、赤と緑のみを使った信号機がアメリカに出てきました。そして、デトロイトの警官が黄色を付け加えたそうです。しかし、当時は手動での操作が必要でした。
1920年には、アメリカのニューヨーク5番街に設置された信号機が設置されました。これが「赤・青・黄」3色のライトを使った世界初の自動交通信号機だといわれています。
このように、交通整理を目的として、改善が繰り返されることより現在の信号機になったんですね。
日本初の信号機
日本初の自動交通信号機は、1930年11月、東京都の日比谷交差点に設置されました。アメリカから輸入したもので、この日本初の信号機設置をきっかけに日本各地に普及していきました。アメリカ製の自動交通信号機導入前までは、標識を手動によって操作することにより交通整理をしていたため、日本に大きな影響をもたらしました。
信号が横向きになった
1930年11月にアメリカから輸入をした日本初の自動交通信号機は縦向きでした。しかし、そのわずか1か月後の1930年12月に、京都の八坂神社前と四条河原町の交差点に横向きの自動交通信号機が交差点の四隅に設置されました。縦向きの信号の場合、看板などの多い京都では視認性に悪影響が出てしまうという理由で、横向きの信号機が採用されたようです。
「縦向き・横向き」の信号機、それぞれメリットとデメリットがあります。
- 縦型信号機:災害(積雪やハリケーン)に強いが視認性は悪い。
- 横型信号機:災害に弱いが視認性は良い。
日本では、横向きの信号機が多いですが、積雪の多い地域では積雪による被害を防ぐために縦向きの信号機にする場合もあるようです。
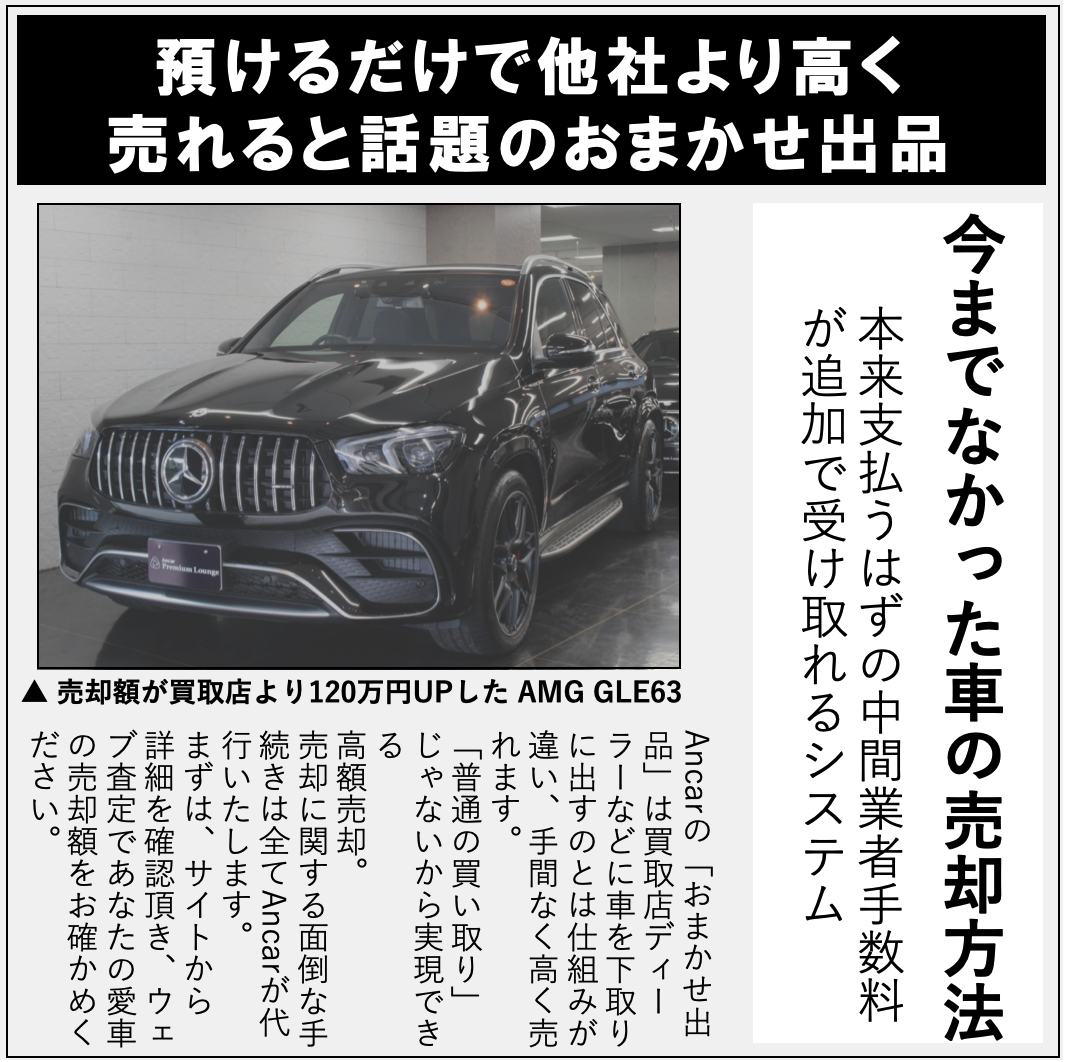
信号の色の由来

信号機の色(赤・青・黄)は、ISO(国際標準化機構)によって、国際的なルールとして定められています。
つまり、世界中どの国に行っても、交通信号機には「赤・青・黄」が使われています。
信号の色が赤青黄の理由
鉄道信号の歴史は古く、交通信号機は鉄道信号を原型にしたといわれています。
- 「赤」:血の色であり、識別しやすいため、鉄道では停止のための色として用いられました。最も重要だと考えられる「止まれ」の指示のために、最も識別しやすい色を採用したのだと考えられます。
- 「緑」:赤の補色であり、見やすい色だったため採用されました。
- 「黄」:色相環で、赤と緑の中間にあたる色で識別しやすいため採用されました。
なんで緑を青って呼ぶの?

緑を青と呼ぶのは日本だけ
交通信号機に用いられる色は、原色の「赤・緑・黄」ですが、なぜ緑のことを青と呼ぶのでしょうか?
そもそも、「緑」を「青」と呼ぶ国は日本だけでした。海外でも日本と同じように緑を青と呼ぶ国がないか調べてみましたが、他の国では色の通り「緑」と呼んでいることがわかりました。
緑色を青信号と呼ぶのは、日本文化の影響を受けたためです。古い日本語において、「青」は広範囲の色をカバーしています。
- 青りんご
- 青野菜
- 青虫
日本では青と緑が区別されたのは平安時代や鎌倉時代だといわれています。そのため、現代においても、緑であっても「青~」と呼ばれるものが多いと考えられます。信号に関しても、同じようなことが由来しています。当初は、法律で「緑信号」と記載されていたようですが、古くからの慣習により、「青信号」と呼ぶ人が多かったため、1947年に正式に「青信号」になったようです。
「青信号」と呼ぶのは日本だけで、古くからの日本語・慣習によってもたらされたと考えると非常に面白いですね。
信号の色の順番はどのように決まった?
信号の色の順番についても考えていきたいと思います。
信号のそれぞれの色の位置:
- 横向きの信号(日本の場合):青、黄、赤
- 縦向きの信号:上から、赤、黄、青
信号の色の順番はどのように決まったのでしょうか。結論からいうと、赤を見やすくするために作られています。事故を防ぐために1番重要な指示は「止まれ」です。必要に応じて、確実に「止まれ」の指示を伝えるには、「赤信号」を最も認識しやすい位置に配置しなければいけません。
縦向き信号の場合は、上が赤の方が認識しやすくなるのはなんとなく想像できると思います。では、なぜ横向きの場合、赤が右に配置されているのでしょうか?横向きの信号機で赤が右側にあるのは、運転手が右側に座るからです。日本と反対で、左ハンドル・右側通行の韓国では、「赤」が1番左側に配置されています。
私たちの知らないところでも、事故を防ぐためにさまざまな工夫がされているんですね。
まとめ
- 信号機はイギリスのロンドンから交通整備を目的として用いられたのがはじまり
- 地域やエリアによって、縦向きと横向きの信号がある
- 交通信号の色は、鉄道信号を原型に「赤・青・黄」が用いられることに
- 信号は赤を見やすいように作られている
信号機は交通事故の発生に大きく関わっていることが理解できたと思います。普段何気なく従っている信号は歴史があり、意外と奥が深いんですね。